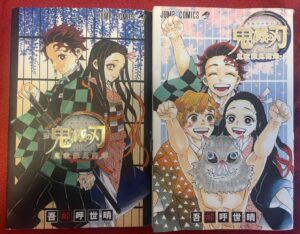「和歌の道=敷島(しきしま)の道」に関する和歌
目次
「敷島(しきしま)の道」とは
和歌の道のことです。
「敷島」は日本のことを指すので、日本人の歩むべき道という意味が含まれています。
鎌倉初期の後鳥羽天皇の頃に定着した言葉だったようです。
鏡が自分の姿を映し出し身なりを整えるのに役立つように、
和歌は自分の心を映し出し、心を整えるのに役立ちます。
自分の心を見つめ直すことになるので、歴代天皇は「しきしまの道」の御修練に努められたそうです。
(『歴代天皇の御製集』「刊行に当たって」に詳しく書かれています。)
白雲のよそに求むな世の人のまことの道ぞしきしまの道 明治天皇
よそに求むな
世の人の
まことの道ぞ
しきしまの道
明治天皇
求めるなかれ
まごころの
道こそ歩む
べき和歌の道
意訳:白雲の彼方(にあるような理想の世界)に(道を)求めるな。この現実の世の人々にとっての目指すべきまごころの道が、しきしまの(日本人の歩むべき和歌の)道である。
★明治三十七年にお詠みになった、詞書「寄道述懐」の歌です。
★上田敏が訳したカール・ブッセの詩「山のあなた」を思い出します。
”山のあなたの 空遠く 「幸(さいわい)」住むと 人のいふ ~”という風に、人は空の向こうに理想を求めてしまいがちなのでしょうね。
それを戒めて、この現実の中で道を求めようとなされたのかなと拝察します。
ふむことのなどかたからむ早くより神のひらきし敷島の道 明治天皇
などかたからむ
早くより
神のひらきし
敷島の道
難しくない
神代から
始まっている
この和歌の道
意訳:歩み、実践することがどうして難しいだろうか、いや、難しくない。(日本の歴史の)早くから神が開拓なさった日本の和歌の道だ。
★明治四十二年にお詠みになった、詞書「寄道述懐」の歌です。
これのみぞ人の国より伝はらで神代をうけし敷島の道 冷泉為相
人の国より
伝はらで
神代をうけし
敷島の道
冷泉為相
他国ではなく
神代から
受け継いできた
日本の道だ
意訳:これだけが他国から伝わっていない、神代から受け継いできた、日本の和歌の道。
★儒教や仏教が他国から伝来されたことに対して、和歌は日本独自の道であることを詠んでいます。
★冷泉為相(ためすけ)は藤原定家の孫。
『十六夜日記』で知られる阿仏尼の第三子で、今にも続いている和歌の名家、冷泉家を興した人物。
もっと学びたい方へ
第一編 「しきしまの道」についての考へ方の研究 ―「しきしまの道」概説―
一 「敷島の道」といふ言葉をめぐって
二 しきしまのみち略史・覚書
三 「皇神の厳しき国、言霊の幸はふ国」
四 国学の流れと「しきしまのみち」
五 皇室と「しきしまのみち」の歴史
第二編 「しきしまの道」の歌論―防人、聖徳太子、明治天皇、井上梧陰、三井甲之ほか―
一 防人を億ふ
二 聖徳太子御歌考
三 人麿の短歌と思想
四 散佚した明治天皇御製(孝明天皇御追悼)四十余首
五 日本の国の国がらについて
六 五浦紀行–岡倉天心の六角堂と三井甲之の「神洲不滅」–
七 「君が代」の語義について
第三編 聖徳太子の御思想と御子・山背大兄王の御一生
第一章 山背大兄王のお墓
第二章 聖徳太子の御逝去とその後の国情
第三章 推古天皇崩御後の皇位継承問題―田村皇子と山背大兄王―
第四章 山背大兄王の御最期
第五章 山背大兄王のお墓(再説)