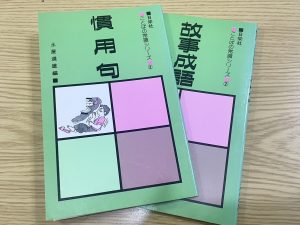令和7年(2025年)宮中歌会始 御製・御歌について
令和7年(2025年)宮中歌会始、お題は「夢」です。
※「夢」に関する過去の御製のご紹介ページもこちらにあります。
目次
御製(ぎょせい/天皇陛下の御歌)旅先に出会ひし子らは語りたる目見輝かせ未来の夢を
旅先に
出会ひし子らは
語りたる
目見輝かせ
未来の夢を
現代語訳(意訳)
旅先で出会った子どもたちは語った。目を輝かせて、未来の夢を。
古典文法・古文単語解説
(出会ひ)し
過去の助動詞「き」の連体形。
(語り)たる
完了の助動詞「たり」の連体形。
※余韻を残す連体形止め(三句切れ)。
目見
①目つき・まなざし ②目もと。
31音口語訳
旅先で
出会った子らは
語ったよ。
目を輝かせ、
未来の夢を。
※ほぼ同じですが、古文だとどうしてもピンとこない方のために作りました。
背景の解説 宮内庁より
天皇皇后両陛下には、例年ご公務や、また、大きな災害があった時には被災地のお見舞いのために、地方に行幸啓になっておられます。昨年は、災害のお見舞いのために石川県を三度ご訪問になった他、地方でのご公務のために、岡山県、佐賀県、岐阜県、大分県の四つの県に行幸啓になり、それぞれの県での行事に出席されました。天皇陛下には、行かれる先々で、県民の皆さんから笑顔で温かく迎えられることを嬉しく思われていることを、昨年の歌会始の御製でお詠みになりました。
今年の御製は、ご訪問先で県民の方々と触れ合われる中で、子どもたちとお話をされることもあり、その子どもさんたちが、自分の将来の夢について生き生きと話す様子を嬉しくお思いになり、その時のご印象を詠まれたものです。
※冒頭の「~には」は、敬意を込めた表現です。
「~におかれましては」の意味で捉えるとわかりやすいです。
※昨年の歌会始の御製はこちら
和歌を味わう
子どもの様子
今上陛下の御製は国民、特に子どもとの触れ合いの中でお感じになったことをお詠みになっていることが多いように拝察します。
これまでの歌会始の御製ですと、令和2、5、6年が国民とのふれあいで、そのうち令和2、5年が子どもたちとのふれあいです。
令和6年(2024年)宮中歌会始(解説はこちら)
をちこちの旅路に会へる人びとの笑顔を見れば心和みぬ
令和5年(2023年)宮中歌会始(解説はこちら)
コロナ禍に友と楽器を奏でうる喜び語る生徒らの笑み
令和4年(2022年)宮中歌会始(解説はこちら)
世界との往き来難かる世はつづき窓開く日を偏に願ふ
令和3年(2021年)宮中歌会始
人々の願ひと努力が実を結び平らけき世の到るを祈る
令和2年(2020年)宮中歌会始
学舎にひびかふ子らの弾む声さやけくあれとひたすら望む
目見(まみ)
「目見(まみ)輝かせ」は同じ五音で「目を輝かせ」がありますが、敢えて古語をお使いになっています。
この古語「目見(まみ)」は<①目つき・まなざし ②目もと>という意味です。
『万葉集』に「大船を荒海に漕ぎ出で弥船綰けわが見し児らが目見は著しも」という和歌があります。
大船を
荒海に漕ぎ出で
弥船綰け
わが見し児らが
目見は著しも
訳:大船を荒海にこぎ出し、船をいよいよ漕ぐが、私の見たあの子の目もとはありありと目に浮かぶことよ。
この歌での「目見(まみ)」はきっと、出航する作者のことを心配している「目見」だっと思います。
今上陛下は行幸で国民をお話しされる際に、相手の「目見(まみ)」からしっかりと心情を受け取っていらっしゃるのでしょうね。
お題「夢」について
「夢」といえば、《将来の夢》か、《寝ているときの夢》が思い浮かびやすいかと思います。
実際にこの、《将来の夢》と《寝ているときの夢》が圧倒的に多かったです。
辞書での「夢」6分類
『精選版 日本国語大辞典』だと、6つに分類されています。
※一部の文言を抜粋
ゆめ【夢】
①睡眠中に、いろいろな物事を現実のことのように見たり聞いたり感じたりする現象。
②覚醒中に視覚的な性質を帯びて現われる空想や想像で、それに引き入れられて放心状態になるようなものをいう。また、非現実的な空想。白昼夢。
③(①を比喩的に用いて) ぼんやりとして不確かなさま、はかないさま、頼みとならないさまなどをいう。
④心のまよい。迷夢。
⑤将来、実現させたいと思っている事柄。将来の希望。思いえがく将来の設計。また、現実ばなれした願望。
⑥現実のきびしさから隔絶した甘い環境や雰囲気。
《将来の夢》は⑤、《寝ているときの夢》は①ですね。
なお、熟語で3首に使われている「夢中」はどの意味にも当てはまらないですね。
その他の熟語「初夢」は①、「白昼夢」は②の意味です。
天皇陛下は《将来の夢》の意味でお使いになっていました。
皇后陛下の御歌は一見、③のようですが、⑤だと思われます。
③だと、時の流れとともにぼんやりと霞んでいく過去の記憶を、はかないものとして捉えた比喩的な使用となります。
ただ、宮内庁の解説に「若き日の志を今ひとたび思い起こされたお気持ち」とあるので、当時抱いていた未来への「夢」を思い起こしているという意味で⑤なのでしょう。
皇后陛下御歌(みうた)三十年へて君と訪ひたる英国の学び舎に思ふかの日々の夢
三十年へて
君と訪ひたる
英国の
学び舎に思ふ
かの日々の夢
現代語訳(意訳)
三十年経って、あなた様と訪れたイギリスの大学に思い起こされた、若き日の志。
古典文法・古文単語解説
君
天皇。
※文脈によって、「あなた」や「主君」などにもなる語ですが、皇后陛下が一緒に歩んで来られたのはもちろん天皇陛下です。
訪ふ
多義語です。ここでは「訪問する」の意味。
(訪ひ)たる
完了の助動詞「たり」の連体形。
和歌を味わう
「君」
「君」という表現は、令和5年(2023年)宮中歌会始(解説はこちら)でもお使いになっていました。
皇室に君と歩みし半生を見守りくれし親しき友ら
平成六年の宮中歌会始でお詠みになった「君と見る波しづかなる琵琶の湖さやけき月は水面おし照る」にも含まれていました。
君と見る
波しづかなる
琵琶の湖
さやけき月は
水面おし照る
ご結婚してまもなく訪れになった琵琶湖畔のホテルの景色をお詠みになった恋の和歌(相聞歌)です💕
「学び舎」
「学び舎(や)」という表現は、天皇陛下が皇太子時代にお詠みになった歌に多数入っています。
平成14年(2002年)
青春をわが過ごしたる学び舎に新入生の声ひびくなり
平成15年(2003年)
オックスフォードのわが学び舎に向かふ時ゆふべの鐘は町にひびけり
平成25年(2013年)
幾人の巣立てる子らを見守りし大公孫樹の木は学び舎に立つ
平成27年(2015年)
山あひの紅葉深まる学び舎に本読み聞かす声はさやけし
こんなに「学び舎」の歌をお詠みになっているのを拝見すると、「学び舎」で詠みたくなりますね。
背景の解説 宮内庁より
天皇皇后両陛下には、お二方とも英国オックスフォード大学で学ばれたご経験がおありになります。天皇陛下には、昭和五十八年から六十年にかけての二年間、オックスフォード大学の大学院で歴史学を学ばれました。皇后陛下には、ご成婚まで外務省に勤務されていた間の在外研修期間中、昭和六十三年から平成二年にかけて、同じく大学院で国際関係論を二年間学ばれました。
両陛下には、昨年六月国賓として英国をご訪問になりました際に、ご一緒にオックスフォード大学を一日お訪ねになりました。皇后陛下にとられては三十四年ぶりとなられたオックスフォード大学ご訪問中に、名誉博士号を授与されるとともに、両陛下がご留学当時にそれぞれ在籍されていたマートン・コレッジとベイリオル・コレッジなど、お懐かしい場所をご一緒にお訪ねになりました。
皇后陛下には、陛下とご一緒にオックスフォード大学を再び訪れることがおできになったことをうれしく、また感慨深く思われるとともに、ご留学当時の様々な想い出を振り返られながら、若き日の志を今ひとたび思い起こされたお気持ちをこのお歌にお詠みになりました。
リンク
令和7年(2025年)宮中歌会始 素敵な歌三選~皇族方の歌編~
令和7年(2025年)宮中歌会始 素敵な歌三選~召人・選者編~